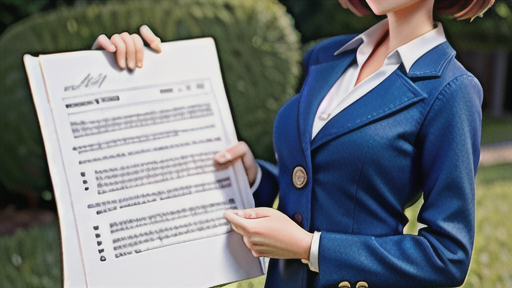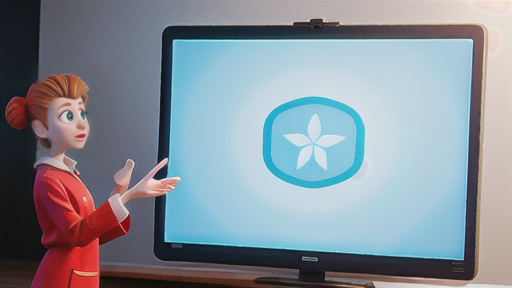リフォーム
リフォーム住宅の強度を支える縁の下の力持ち「根がらみ貫」
家を建てるには、実に様々な材料が使われます。壁や屋根など目に見える部分だけでなく、家の骨組みとなる構造も、たくさんの部材が組み合わさってできています。その中で、今回は普段あまり目にすることはありませんが、家の強度を保つために重要な役割を果たしている「根がらみ貫」についてお話します。根がらみ貫は、主に木材で作られた横架材の一種です。家の構造の中でも、柱の下部や床束を水平方向に繋ぐように設置されます。地震や強風など、外部から力が加わった際に、この根がらみ貫が家全体のバランスを保ち、歪みや倒壊を防ぐ重要な役割を果たします。根がらみ貫は、家の構造をしっかりと支え、安定させる縁幕の役割を果たしていると言えるでしょう。見えない部分ながらも、家を守る大切な部材の一つなのです。